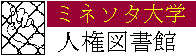
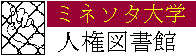
拷問及び非人道的な又は品位を傷つける取扱い
又は刑罰の防止のためのヨーロッパ条約
(拷問等防止ヨーロッパ条約)(抄)
効力発生 一九八九年二月一日
欧州評議会加盟国であるこの条約の署名政府は、
人権及び基本的自由の保護のための条約の諸規定を考慮し、
同条約の第三条の下では「何人も、拷問又は非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い又は刑罰を受けない」ことを想起し
同条約に規定する制度、第三条の違反の被害者であると主張する者については効果がないことを留意し、
自由を奪われた者を拷問又は非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い又は刑罰から保護することは、訪問を基礎とする防止的性質の非法律的手段によって強化されうると確信して、
次のとおり協定した。
第一章 拷問等防止委員会
第一条 設置、目的
「拷問又は非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い又は刑罰の防止のためのヨーロッパ委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、訪問の手段によって、必要なときは自由を奪われた者の拷問及び非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰からの保護を強化するために、それらの者の取扱いを審査する。
第二条 訪問の許可
各締約国は、この条約に従って、その管轄の下にある場所であって人が公の当局によって自由を奪われているいずれの場所への訪問も許可しなければならない。
第三条 協力
この条約の適用に当たっては、委員会及び関係締約国の権限のある国内当局は、相互に協力しなければならない。
第二章 委員会の構成
第四条 構成
1 委員会は、締約国数と同数の委員で構成する。
2 委員会の委員は、高潔な人格を有し、人権の分野で有能の名のある者又はこの条約が取り扱う領域において専門的な経験を有する者の中から選出される。
3 委員会のいずれの二人の委員も、同一国の国民であってはならない。
4 委員は、個人の資格で職務を遂行し、独立かつ公平でなければならず、また、委員会に有効に奉仕するために利用できなければならない。
第五条 選挙
1 委員会の委員は、欧州評議会協議総会の事務局が作成した名簿の中から、投票の絶対多数によって欧州評議会閣僚委員会により選出される。協議総会における各締約国の代表者団は、三人の候補者を推薦し、そのうち少なくとも二人はその国の国民とする。
欧州評議会の非加盟国について委員が委員会に選出されるべき場合には、協議総会の事務局は、当該国の議会に対して三人の候補者を推薦するように招請し、その内少なくとも二人はその国の国民とする。閣僚委員会による選挙は、関係国との協議の後行われる。
2 偶然の空席を補充するに当たっては、同一の手続がとられなければならない。
3 委員会の委員は、四年の任期で選出される。委員は、二度再選されることができる。ただし、第一回の選挙において選出された委員のうち三人の委員の任期は、二年の終わりに終了する。最初の二年の期間の終わりに任期が終了する委員は、第一回の選挙が完了した後直ちに、欧州評議会事務総長によりくじ引きで選ばれる。
4 委員会の委員の半数ができる限り二年ごとに更新されることを確保するために、閣僚委員会は、次の選挙を実施する前に、選出されるべき一又はそれ以上の委員の任期を二年以上六年以内であって四年以外の任期とすることを決定することができる。
5 一期を越える場合であってかつ閣僚委員会が1を適用する場合には、任期の配分は、選挙の後直ちに事務総長によるくじ引きにより行われる。
第六条 委員会の会合
1 委員会は、非公開で会合する。定足数は、委員の過半数と同数である。委員会の決定は、第一〇条2の規定に従うことを条件として、出席した委員の過半数によって行う。
2 委員会は、手続規則を作成する。
3 委員会の事務局は、欧州評議会事務総長によって提供される。
第三章 委員会の活動
第七条 訪問
1 委員会は、第二条に規定する場所への訪問を組織する。委員会は、定期的訪問のほか、状況により必要と思われるその他の訪問を組織することができる。
2 訪問は、原則として、委員会の少なくとも二名の委員によって実施される。委員会は、必要と考える場合には、専門家及び通訳の援助を受けることができる。
第八条 便宜供与
1 委員会は、当該締約国政府に訪問を実施する意図を通知しなければならない。委員会は、そのような通知の後に、第二条に規定する場所をいつでも訪問することができる。
2 締約国は、任務を遂行するために次の便宜を委員会に与えなければならない。
(a) 領域への立入り及び制限なしに旅行する権利
(b) 自由を奪われた者が抑留されている場所に関する十分な情報
(c) 人が自由を奪われているあらゆる場所への無制限な立入り(制限なしにそのような場所の内部を移動する権利を含む。)
(d) 委員会がその任務を実施するために必要な情報で、当該締約国が入手できるもの。委員会は、そのような情報を入手する際に、国内法の適用可能な規則及び職業上の倫理に考慮を払わなければならない。
3 委員会は、自由を奪われた者と内密に面談することができる。
4 委員会は、関連のある情報を提供できると考えるいずれの者とも自由に通信することができる。
5 委員会は、必要な場合には、当該締約国の権限のある当局に対して直ちに意見を通報することができる。
第九条 異議申立
1 当該締約国の権限のある当局は、例外的状況の場合には、委員会が提案した時期又は特定の場所への訪問について、委員会に異議申立をすることができる。そのような異議申立は、国の防衛、公共の安全、人が自由を奪われている場所の重大な混乱、その者の医学的状態、又は、重大な犯罪に関係する緊急の尋問が進行中であることを理由としてのみ行うことができる。
2 そのような異議申立の後に、委員会及び当該締約国は、事態を明確にしかつ委員会がその任務を迅速に行うことを可能ならしめるための準備に関する合意を得るために、直ちに協議に入らなければならない。そのような準備は、委員会が訪問することを提案した者の他の場所への移送を含むことができる。当該締約国は、訪問が行われるまで、その者について委員会に情報を提供しなければならない。
第一〇条 報告
1 委員会は、各訪問の後に、当該締約国によって提示されることのある意見を考慮して、訪問中に判明した事実に関する報告を作成しなければならない。委員会は、必要と考える勧告を含む報告を当該締約国に送付しなければならない。委員会は、必要な場合には自由を奪われたものの保護に関する改善を提案するために、当該締約国と協議することができる。
2 当該締約国が委員会の勧告に照らして事態を改善するために協力しないか又は拒否した場合には、委員会は、当該締約国が自国の見解を知らせる機会を得た後に、委員会の三分の二の多数によりその問題に関する公式声明を行うことを決定することができる。
第一一条 情報などの非公開
1 訪問に関連して委員会が収集した情報、報告及び当該締約国との協議は、非公開とする。
2 委員会は、当該締約国が要請したときはいつでも、報告をその国の見解と共に公表しなければならない。
3 ただし、個人の資料は、その者の明示的な同意がなければ、公表してはならない。
第一二条 活動の一般報告
委員会は、第一一条の非公開の規則に従うことを条件として、毎年閣僚委員会に対してその活動に関する一般報告を提出するものとし、この一般報告は、協議総会及び条約の締約国である欧州評議会の非加盟国に送付され、公表される。
第一三条 守秘義務
委員会の委員、委員会を援助する専門家その他の者は、その任期中及び任期後も、任務遂行中に知り得た事実又は情報の非公開性を維持するよう要求される。
第一四条 援助者
1 委員会を援助する者の名前は、第八条1に基づく通知の中に明示されなければならない。
2 専門家は、委員会の訓令に基づきかつその権威の下に行動する。専門家は、この条約が対象とする領域において特別の知識及び経験を有していなければならず、かつ、委員会の委員と同一の独立、公平及び有効性の義務によって拘束される。
3 締約国は、委員会を援助する専門家又はその他の者が自国の管轄の下にある場所への訪問に参加することを許されない旨宣言することができる。
第四章 雑則
第一五条 通知受領者
各締約国は、自国政府に対する通知を受領する権限のある当局及びその国が任命することのある連絡員の名前及び住所を委員会に通知しなければならない。
第一六条 特権免除
委員会、委員及び第七条2に規定する専門家は、この条約の附属書に定める特権及び免除を享有する。
第一七条 保護の基準
1 この条約は、自由を奪われた者に対して一層広い保護を与える国内法又は国際協定の規定の適用を害するものではない。
2 この条約中の何ものも、ヨーロッパ人権条約の諸機関の権限若しくはその条約に基づいて締約国が負う義務を制限し又は免脱するものと解釈してはならない。
3 委員会は、一九四九年八月一二日のジュネーヴ諸条約及びそれに対する一九七七年六月八日の追加議定書によって利益保護国又は赤十字国際委員会の代表が定期的に効果的に訪問している場所を訪問してはならない。
第五章 最終規定
第一八条 署名、批准及び寄託 (略)
第一九条 効力発生 (略)
第二〇条 適用地域 (略)
第二一条 留保の禁止 (略)
第二二条 廃棄 (略)
第二三条 欧州評議会事務総長による通報 (略)
附属書 特権及び免除
1 この附属書の適用上、委員会の委員への言及は、第七条2にいう専門家への言及を含むものとみなされなければならない。
2 委員会の委員は、その任務を遂行している間及び任務遂行中に行う旅行の間、次の特権及び免除を享有する。
(a) 身体の抑留又は拘禁及び手荷物の押収からの免除、並びに、語った言葉又は書いた文書及びその公的資格において行ったすべての行為については、あらゆる種類の法的手続からの免除
(b) 移動の自由(居住国からの出国及びその国への帰国並びに任務を遂行する国への入国及びその国からの出国)に対する制限からの免除、及び、訪問する国又は任務遂行中に通過する国における外国人登録からの免除
3 委員会の委員は、任務遂行中に行う旅行の間、関税及び為替管理の事項について次のものをあたえられる。
(a) 自国政府により、一般的な公務で外国旅行をする上級官吏に与えられるものと同一の便宜
(b) 他の締約国政府により、一時的な公務を行う外国政府代表に与えられるものと同一の便宜
4 委員会の文書及び書類は、それらが委員会の業務に関係する限り、不可侵とする。
委員会の公用通信その他の公用連絡は、留置し又は検閲することができない。
5 委員会の委員に対して職務の遂行中の完全な発言の自由及び完全な独立を保障するために、語った言葉又は書いた文書及び職務の遂行中に行ったすべての行為についての法的手続からの免除は、その委員がもはやそのような職務の遂行に従事していない場合にも、引き続き与えられなければならない。
6 特権及び免除は、個人の利益のためではなく、任務の独立した遂行を保障するために、委員会の委員に与えられるものである。委員会のみが、委員の免除を放棄する権限を有する。委員会は、免除が正義の前進を妨げると考える場合、及び、免除が与えられた目的を害することなく放棄できる場合には、一人の委員の免除を放棄する権利を有するのみならず、その義務を負う。
出典 東信堂 「国際人権条約・宣言集 第三版」より抜粋・編集