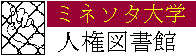
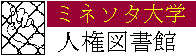
教育における差別待遇の防止に関する条約の締約国間に 生ずることのある紛争の解決を求める責任を有する 調停斡旋委員会を設立する議定書(仮訳)
1962年12月10日 第12回ユネスコ総会 採択 1968年10月24日 効力発生
国際連合教育科学文化機関の総会は、
1962年11月9日から12月12日までパリでその第12回会期として会合し、その第11回会期において教育における差別待遇の防止に関する条約を採択したので、その条約の実施を容易にすることを希望し、この目的のためには、条約の締約国間に条約の適用又は解釈に関して生ずることのある紛争の和解を求める責任を有する調停あっせん委員会を設立することが重要であることを考慮し、1962年12月10日にこの議定書を採択する。
第 1 条
教育における差別待遇の防止に関する条約(以下「条約」という。)の適用又は解釈に関する締約国間の紛争の和解を求める責任を有する調停あっせん委員会(以下「委員会」という。)を、国際連合教育科学文化機関の保護のもとに設置する。
第 2 条
1 委員会は、徳望が高く、かつ、公平無私で知られた者のうちから国際連合教育科学文化機関の総会(以下「総会」という。)が選挙する11人の委員で構成する。
2 委員会の委員は、個人の資格において勤務する。
第 3 条
1 委員会の委員は、この議定書の締約国が選挙の目的のために指名した者の名簿から選挙されるものとする。各締約国は、その国のユネスコ国内委員会と協議の後、4人を越えない者を指名する。これらの者は、この議定書の締約国の国民でなければならない。
2 国際連合教育科学文化機関事務局長(以下「事務局長」という。)は、委員会委員の毎回の選挙の日の少なくとも4箇月前に、この議定書の締約国に対し、前項の者についてのその指名を2箇月以内に回報するよう勧奨するものとする。事務局長は、このようにして指名を受けた者のアルファベット順の名簿を作成し、これを、選挙の少なくとも1箇月前に、国際連合教育科学文化機関の執行委員会(以下「執行委員会」という。)及び条約の締約国に提出するものとする。執行委員会は、この名簿を、有用と認める示唆を付して総会に送達し、総会は、2人以上の選挙について総会が正常に従う手続に従って、委員会の委員の選挙を実施するものとする。
第 4 条
1 委員会は、同一国の国民を1人をこえて委員とすることができない。
2 委員会の委員を選挙するにあたり、総会は、教育の分野において有能の名のある者及び特に国際的性格の司法上の経験又は法律上の経験を有する者を含めるように努力しなければならない。総会は、また、委員の公正な地理的分布並びに各種の文明形態及び主要法系が代表されるべきものであることにも考慮を払わなければならない。
第 5 条
委員会の委員は、6年の任期で選挙されるものとする。委員会の委員は、再指名されたときは、再選されることができる。もっとも、第1回の選挙において当選した委員のうち4人の任
期は、2年の終了の時に満了するものとし、他の3人の任期は、4年の終了の時に満了するものとする。それらの委員は、第1回の選挙の直後に、総会議長がくじで選ぶ。
第 6 条
1 委員会の委員に死亡し又は辞任した者があるときは、委員長は、直ちに事務局長に通告するものとし、事務局長は、その席がその死亡の日又は辞任が効力を生ずる日から欠員であると宣言するものとする。
2 委員会の一委員が、他の委員の全員一致の意見により、一時的性格の欠席以外の原因によりその任務の遂行を停止したとされ、又は任務の遂行の継続が不能であるとされたときは、委員長は事務局長に通告し、かつ、その後ただちに、当該委員の席が欠員であると宣言するものとする。
3 事務局長は、前2項の規定によって生じた欠員につき、国際連合教育科学文化機関の加盟国及び機関の加盟国ではないが第23条の規定によりこの議定書の締約国になっている国家に通報するものとする。
4 第1項及び第2項の規定に該当する場合が生じたときは、そのつど、総会は、次員となった席を占めていた委員の任期の残存期間につき、後任者を定めるものとする。
第 7 条
前条の規定に従うことを条件として、委員会の委員は、その後任者の就任の時まで職に留まる。
第 8 条
1 第12条又は第13条の規定により委員会に付託された紛争の当事国である国家の国民が委員会の委員となっていない場合は、その国家(2以上である場合は、そのおのおのとする。)は、特別委員として出席する者を1人選任することができる。
2 前項の規定により特別委員を選任する国家は、第2条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定により委員会の委員に求められる資格に顧慮を払わなければならない。特別委員は、これを選任する国家又はこの議定書の締約国の国民でなければならず、かつ、個人の資格で勤務するものとする。
3 利害関係を同じくする紛争当事国が数国あるときは、それらの当事国は、特別委員の選任に関しては、単一の当事者とみなす。この規定の適用の仕方は、第11条の委員会手続規則で定める。
第 9 条
委員会の委員及び前条の規定により選任された特別委員は、委員会の作業に従事している期間につき、国際連合教育科学文化機関の財源から、執行委員会の定めるところにより、旅費及び手当を受ける。
第 10 条
委員会の事務局は、事務局長が提供する。
第 11 条
1 委員会は、委員長及び副委員長を各1人2年の任期で選挙する。委員長及び副委員長は、再選されることができる。
2 委員会は、その手続規則を定めるものとする。この手続規則は、特に次のことを規定しなければならない。
(a) 委員(特別委員がある場合は、これを含む。)の3分の2が定足数を構成すること。
(b) 委員会の議事は、出席した委員及び特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによること。
(c) ある国家が次条又は第13条の規定に基づいて事件を付託するときは、
(i) その国家、不服の被申立国及びその事件に自国民が関係しているこの議定書の締約国は、委員会に対し、書面によるサブミッションを行なうことができること。
(ii) その国家及び不服の被申立国は、事件の審理にあたって代表者を出席させる権利及び口頭でサブミッションを行なう権利を有すること。
3 委員会は、その手続規則の制定を最初に提案するに際しては、その時にこの議定書の締約国である国家に手続規則案を送付するものとし、それらの国家は、所見及び示唆を3箇月以内に回報することができるものとする。委員会は、この議定書のいずれかの締約国の要請があったときは、随時、手続規則の再検討を行なうものとする。
第 12 条
1 この議定書の締約国は、他の締約国が条約の規定に効果を与えていないと考えるときは、そのことにつき、その国の注意を文書によって喚起することができる。その文書を受領した国家は、受領後3箇月以内に、問題を提起した国家に対し、そのことに関する説明書又は陳述書を与えなければならない。この説明書又は陳述書は、可能であり、かつ、適切である限りにおいて、そのことについて講じられ若しくは審理中の又は用いうる手続及び矯正措置に言及すべきものとする。
2 事態が、文書を受領した国家が最初の文書を受領した後6箇月以内に、2国間の交渉により又はその他の利用可能な手続により、両当事国を満足させるように調整されないときは、どちらの国家も、事務局長及び相手国に通告することにより事件を委員会に付託する権利を有するものとする。
3 前項の規定は、締約国が、当該国間において現行の一般的な又は特別な国際協定の規定に従って、紛争解決のための他の手続(相互の同意によりヘーグにある常設仲裁裁判所に紛争を付託する手続を含む。)を用いる権利に影響するものではない。
第 13 条
この議定書の発効後6年目の初めから、委員会は、条約の締約国ではあるがこの議定書の締約国ではない国家(一部が議定書の締約国である場合を含む。)の間に生ずる条約の適用又は解釈に関する紛争につき、当該国が当該紛争を委員会に付託することに同意する場合は、その解決を求める責任も負わせられることができる。そのような国が同意に達するために充足すべき条件は委員会の手続規則で定める。
第 14 条
委員会は、前2条の規定により事件の付託を受けたときは、その件についてはすべての使用可能な国内的矯正措置が、一般的に認められている国際法の諸原則に従って、執られ、かつ、使い尽くされたことを委員会が確かめた後に限り取り扱うものとする。
第 15 条
委員会は、新しい要素が委員会に提出された場合を除いて、すでに取り扱った事件を審理してはならない。
第 16 条
委員会は、付託を受けた事件のいずれについても、関係国に対し、関係情報の供給を要請することができる。
第 17 条
1 第14条の規定に従うことを条件として、委員会は、その必要と認める情報をすべて入手し
た後、事実を確かめ、条約の尊重を基礎とした当該事件の円満な解決をはかるため、関係国にあっせんを提供するものとする。
2 委員会は、いずれの事件についても、第12条第2項の通告を事務局長が受け取った日の後18箇月以内に、次項の規定による報告書を作成してこれを関係国に送付し、次いで公表のため事務局長に伝達するものとする。次条の規定により国際司法裁判所の勧告的意見を求めるときは、期限は、適宜延期されるものとする。
3 委員会は、第1項の規定による解決が得られたときは、その報告書の内容を、事実及び得られた解決の簡単な陳述に限定するものとする。そのような解決が得られないときは、委員会は、事実に関する報告書を作成し、和解のために委員会が行なった勧告について記述するものとする。その報告書がその全部又は一部について委員会の委員の全員一致の意見を表明していないときは、いずれの委員も、個別の意見をその報告書に添付する権利を有する。第11条第2項(c)の規定に従って当事国が書面及び口頭で行なったサブミッションは、報告書に添付するものとする。
第 18 条
委員会は、執行委員会に対し、又は、総会の会期が2箇月以内に開会されるときは総会に対し、委員会に付託された事件に関するいずれの法律問題についても、国際司法裁判所の勧告的意見を求めることを勧告することができる。
第 19 条
委員会は、その活動に関する報告書を、総会に対し、その通常会期ごとに提出するものとする。その報告書は、執行委員会が、総会に送達する。
第 20 条
1 事務局長は、総会の指名後3箇月以内に、委員会の第1回会議を、国際連合教育科学文化機関の本部に招集する。
2 委員会のその後の会議は、必要のつど、委員会の委員長が招集する。事務局長は、この議定書の規定に従って委員会に付託されたすべての事件につき、委員長及び全委員に送達する。
3 前項の規定にかかわらず、委員会の委員の少なくとも3分の1が、この議定書の規定に従ってある事件を委員会が検討すべきであると考える場合において、それらの委員が要請したときは、委員長は、その目的のために委員会の会議を招集するものとする。
第 21 条
この議定書は、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語で起草する。これらの4本文は、 ひとしく正文とする。
第 22 条
1 この議定書は、条約の締約国である国際連合教育科学文化機関の加盟国により、批准され又は受諾されなければならない。
2 批准書又は受諾書は、事務局長に寄託されるものとする。
第 23 条
1 この議定書は、条約の締約国ではあるが、国際連合教育科学文化機関の加盟国ではないすべての国家の加入のために開放しておく。
2 加入は、事務局長に加入書を寄託することによって効力を生ずる。
第 24 条
この議定書は、15番目の批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の3箇月後に、その日以前に文書を寄託した国家についてだけ効力を生ずる。この議定書は、その他の国家については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の3箇月後に効力を生ずる。
第 25 条
いずれの国家も、批准、受諾若しくは加入の時に、又はその後いつでも、事務局長に対する通告により、この議定書の対象となる紛争で第17条第1項の規定による和解が成立しないものについて、第17条第3項の規定による報告書の起草の後に、国際司法裁判所に付託することを、同一の義務を受諾する他の国家に対する関係において合意することを宣言することができる。
第 26 条
1 この議定書の締約国は、この議定書を廃棄することができる。
2 廃棄は、通告書を事務局長に寄託することによって行なうものとする。
3 条約の廃棄は、自動的にこの議定書の廃棄を伴う。
4 廃棄は、廃棄書の受領の12箇月後に効力を生ずる。もっとも、議定書を廃棄する国家は、本項に定める期限の終了前に委員会に付託された当該国関係事件については、この議定書の規定になお拘束されるものとする。
第 27 条
事務局長は、第22条及び第23条の規定による全ての批准書、受諾書及び加入書の寄託につき、並びに第25条の規定による通告及び前条の規定による廃棄につき、国際連合教育科学文化機関の加盟国、第23条の機関非加盟国及び国際連合に通報するものとする。
第 28 条
この議定書は、国際連合憲章第102条の規定に従って、事務局長の要請に基づいて国際連合事務局に登録されるものとする。
1962年12月18日にパリにおいて国際連合教育科学文化機関の総会の第12回会期の議長及び事務局長の署名を有する正文2通を作成した。両正文は、国際連合教育科学文化機関の記録に寄託しておく。両正文の認証謄本は、条約第12条及び第13条のすべての国家並びに国際連合に送達されるものとする。
以上は、国際連合教育科学文化機関総会が、パリで開催されて1962年12月12日に閉会を宣言されたその第12回会期において正当に採択した議定書の真正な本文である。
以上の証拠として、われわれは、1962年12月18日に署名した。
総 会 議 長
パウロ・E・ド・ベレド・カルネイロ
事 務 局 長
ルネ・マウ