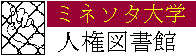
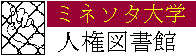
教育における差別待遇の防止に関する条約(仮訳)1960年12月14日 第11回ユネスコ総会 採択 1962年 5月22日 効力発生
国際連合教育科学文化機関の総会は、
1960年11月14日から同年12月15日までパリにおいてその第11回会期として会合し、世界人権宣言が、無差別の原則を主張し、かつ、すべて人は教育を受ける権利を有すると宣言していることを想起し、教育における差別待遇がこの宣言に言明された権利の侵害であることを考慮し、国際連合教育科学文化機関が、その憲章の条項のもとにおいて、人権の普遍的尊重及び教育の機会均等をすべての人のために助長するための諸国民間の協力の関係をつくる目的を有することを考慮し、したがって、国際連合教育科学文化機関が、各国の教育制度の多様性を尊重しつつも、教育における差別待遇はいかなる形態のものも排除する義務だけでなく、教育の機会及び待遇の平等をすべての人のために促進する義務も有することを認識し、この会期の議事日程の第17.1.4議題である教育における差別待遇の種々の面に関する提案を審議し、この問題を国際条約及び加盟国に対する勧告として規制すべきことを第10回会期において決定したので、1960年12月14日にこの条約を採択する。
第 1 条
1 この条約の適用上、「差別」には、何らかの区別、除外、制限又は優遇であって、人種皮ふの色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、経済的条件又は門地に基づき、教育における待遇の平等を無効にし又は害すること、及び、特に次に掲げることを目的又は結果として有するものを含む。
(a) いずれかの種類又は段階の教育を受ける機会を個人又は個人の集団から奪うこと。
(b) 個人又は個人の集団を水準の低い教育に限定すること。
(c) 次条の規定に従うことを条件として、個人又は個人の集団のための別個の教育制度又は教育機関を設け又は維持すること。
(d) 人間の尊厳と両立しない条件を個人又は個人の集団に課すること。
2 この条約の適用上、「教育」とは、すべての種類及び段階の教育をいい、かつ、教育を受ける機会、教育の水準及び質、並びに教育が与えられる条件を含む。
第 2 条
次に掲げる状態は、一国において許されている場合は、前条の意味における差別を構成するものとはみなさない。
(a) 両性の生徒のための別個の教育制度又は教育機関の設置又は維持。ただし、その制度又は機関が、教育の均等な機会を提供し、同じ水準の資格を有する教育職員及び同質の校舎と設備を提供し、かつ、同一又は同等の教育課程を履修する機会を与える場合に限る。
(b) 宗教上又は言語上の理由により、生徒の両親又は法定後見人の希望に応じた教育を提供する別個の教育制度又は教育機関の設置又は維持。ただし、その制度への参加又はその機関への通学が任意であり、かつ、与えられる教育は権限のある当局が、特に同じ水準の教育のため、定め又は承認することのある基準に適合する場合に限る。
(c) 私立の教育機関の設置又は維持。ただし、その機関の目的が、いずれかの集団の排除を確保するためではなく、公共当局が提供する教育施設のほかに教育施設を提供することにあり、その機関がこの目的にそって運営され、かつ、与えられる教育は権限のある当局が、特に同じ水準の教育のため、定め又は承認することのある基準に適合する場合に限る。
第 3 条
この条約の意味における差別を除去し及び防止する為、締約国は、次のことを約束する。
(a) 教育上の差別をもたらす法令の規定及び行政上の通達を廃止し、並びにそのような差別をもたらす行政上の慣行を停止すること。
(b) 必要な場合には法律の制定により、教育機関への生徒の入学について差別が行なわれないようにすること。
(c) 授業料について、並びに生徒に対する奨学金その他の形態の援助の供与並びに外国で研究を続行するために必要な許可及び便宜の供与について、成績又は需要に基づく場合のほか、国民の間に公共当局による待遇の差別を許さないこと。
(d) 公共当局が教育機関に与えるいかなる形態の援助においても、生徒が特定の集団に属することだけを根拠とした制限又は優遇を許さないこと。
(e) 自国の領域内に居住する外国人に対し、自国民に対して与えるものと同じ教育の機会を与えること。
第 4 条
締約国は、さらに、実情及び国民的慣習に適合した方法を講ずれば教育に関する機会の平等と待遇の平等の促進に資し、並びに特に次のことに資する国内政策を策定し、発展させ及び実施することを約束する。
(a) 初等教育を、無償で、かつ、義務制とすること。種々の形態の中等教育を、広く行なわれ、かつ、すべての人が受ける権利を持つものとすること。高等教育を、個人の能力を基礎としてすべての人がひとしく受ける権利を持つものとすること。法律に規定された就学の義務のすべての人による履行を確保すること。
(b) 教育の水準が同じ段階のすべての公立教育機関において同等であることを確保すること、及び、与えられる教育の質に関する条件も同等であることを確保すること。
(c) 初等教育を受けなかった者又は初等教育の全課程を修了しなかった者の教育と、個人の能力を基礎としたこれらの者の教育の継続とを、適当な方法によって奨励し及び強化すること。
(d) 教職のための訓練を差別なしに提供すること。
第 5 条
1 締約国は、次のことに同意する。
(a) 教育は、人格の円満な発達並びに人権及び基本的自由の尊重の念の強化に向けられなければならないものであること。教育は、すべての国の国民、人種的集団又は宗教的集団相互の間における理解、寛容及び友情を促進し、かつ、平和維持のための国際連合の諸活動を助長しなければならないものであること。
(b) 両親及び該当する場合は法定後見人の自由、すなわち、第1には、公共当局が維持する機関以外の機関であって権限のある当局が定め又は承認することのある最低限の教育水準に適合するものを子弟のために選択する自由、並びに、第2には、その国の法令の適用のために国内でとられる手続にそった方式により、自己の信念に一致した子弟の宗教教育及び道徳教育を確保する自由を尊重することが肝要であること。また、いかなる個人又は個人の集団も、自己の信念と両立しない宗教教育を受けることを強要されてはならないこと。
(c) 次に掲げる条件が整う場合は、少数民族の構成員が自己の教育活動(学校の維持及び、当該国の教育政策のいかんによっては、少数民族の言語の使用又は教授を含む。)を行なう権利を認めることが肝要であること。
(i) この権利が、当該少数民族の構成員による共同社会全体の文化と言語との理解及び共同社会全体の活動への参加を妨げるような方式又は国家主権を害するような方式で行使されないこと。
(ii) 教育の水準が、権限のある当局が定め又は承認した一般的水準よりも低くないこと。
(iii) このような学校への就学が、任意であること。
2 締約国は、前項の諸原則の適用を確保するために必要ないっさいの対策を講ずることを約束する。
第 6 条
締約国は、この条約の適用にあたり、国際連合教育科学文化機関総会が今後採択する勧告であって教育における各種の形態の差別を防止し、かつ、教育における機会と待遇との平等を確保するために執るべき措置を定めるものに最大の注意を払うことを約束する。
第 7 条
締約国は、国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限及び様式により総会に提出する定期報告の中で、この条約の適用のために採択した立法上及び行政上の規定並びに執った他の措置(第4条の国内政策の策定及び発展のために執った措置、並びにその政策の適用にあたって達成された結果及び遭遇した障害を含む。)に関する情報を提供しなければならない。
第 8 条
この条約の解釈又は適用に関して2以上の締約国間に生起した紛争で交渉により解決することができないものは、他に紛争解決の手段がない場合は、当事国の要請に基づき、決定のため国際司法裁判所に付託するものとする。
第 9 条
この条約には、いかなる留保も認めない。
第 10 条
この条約は、2以上の国家間において締結された協定に基づいて個人又は集団が享有する権利がこの条約の文字又は精神に反しない場合は、その権利を縮少する効力を有するものとされてはならない。
第 11 条
この条約は、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語で起草する。これらの4本文は、
ひとしく正文とする。
第 12 条
1 この条約は、国際連合教育科学文化機関の加盟国により、各自の憲法上の手続に従って批准され又は受諾されなければならない。
2 批准書又は受諾書は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託されるものとする。
第 13 条
1 この条約は、国際連合教育科学文化機関の加盟国ではない国家であって機関の執行委員会によって加入を勧奨されるものすべての加入のために開放しておく。
2 加入は、国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって効力を生ずる。
第 14 条
この条約は、3番目の批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の3箇月後に、その日以前に文書を寄託した国家についてだけ効力を生ずる。この条約は、その他の国家については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の3箇月後に効力を生ずる。
第 15 条
締約国は、この条約がその本土だけでなく自国が国際関係について責任を有する非自治地域、信託地域、植民地及びその他の地域のすべてにも適用されるものであることを認める。締約国は、それらの地域へのこの条約の適用を確保するために必要な場合は、批准、受諾又は加入の事前又は事後に、それらの地域の政府又はその他の権限のある当局に協議すること、及び、この条約が適用される地域について国際連合教育科学文化機関事務局長に通告することを約束する。
第 16 条
1 各締約国は、自国のために、又は自国が国際関係について責任を有する地域のために、この条約を廃棄することができる。
2 廃棄は、通告書を国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託することによって行なうものとする。
3 廃棄は、廃棄書の受領の12箇月後に効力を生ずる。
第 17 条
国際連合教育科学文化機関事務局長は、機関の加盟国、第13条の非加盟国及び国際連合に対し、第12条及び第13条の規定に基づくすべての批准書、受諾書及び加入書の寄託について、並びに第15条の規定に基づく通告及び第16条の規定に基づく廃棄について通報するものとする。
第 18 条
1 この条約は、国際連合教育科学文化機関の総会によって改正されることができる。もっと
も、その改正は何れも、その改正する条約の締約国となる国家だけを拘束するものとする。
2 総会がこの条約の全部文は一部を改正する新しい条約を採択したときは、その新しい条約に別段の規定がある場合を除いて、この条約は、新しい改正条約が効力を生ずる日から、批准、受諾又は加入への開放を停止する。
第 19 条
この条約は、国際連合憲章第102条の規定に従って、国際連合教育科学文化機関事務局長の要請に基づいて国際連合事務局に登録されるものとする。
1960年12月15日にパリにおいて国際連合教育科学文化機関の総会の第11回会期の議長及び事務局長の署名を有する正文2通を作成した。両正文は、国際連合教育科学文化機関の記録に寄託しておく。両正文の認証謄本は、第12条及び第13条のすべての国家並びに国際連合に送達されるものとする。
以上は、国際連合教育科学文化機関総会がパリで開催されて1960年12月15日に閉会を宣言されたその第11回会期において正当に採択した条約の真正な本文である。
以上の証拠として、われわれは、1960年12月15日に署名した。
総 会 議 長
アカレウオルク・アプテウオルド
事 務 局 長
ヴィトリノ・ヴェロネーゼ